●エレキの品格
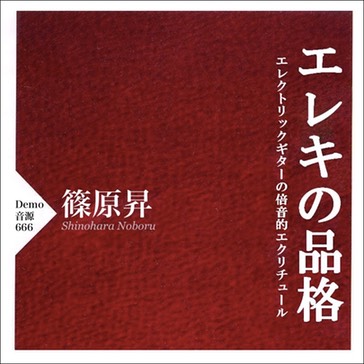
左の画像はだいぶ前にPHP新書のベストセラー本の表紙をパクって作ったもの。正方形に整えて、画像加工ソフトの「ニキビとかを消す機能」で文字を削除して、その上にタイトルと名前を書き込んだ。楽しかった。
エレクトリックギターはとてもインチキくさい楽器だと思う。まず電気がないと音が出ない。火力発電だとか原子力発電だとかいった、功罪大きい設備が稼働してくれているおかげでやっと音が出せる。現代人は生まれてから死ぬまで、ほとんど電気なしではもう暮らしていけないだろう。この呪われた現代人の宿命を象徴した楽器なのだ。だから興味を持ったのだと思う。電気を使わない歴史ある楽器にはなぜか興味が向かなかった。
エレキという略称は、どうにも救いようがない。昔は「エレキはチンピラの楽器」「ロックは悪魔の音楽」とか言われていたらしい。「エレキ」と略した昭和世代の罪は非常に大きい。よくもここまで薄っぺらく、侮蔑的で、自嘲的で、音楽的豊かさを期待できない響きを考えたものだ。サブカルチャーの立場に甘んじて永久に地位が上がることはないと思う。しかし、だからこそ、このインチキくさい楽器でどれくらいの音楽表現ができるのかを追求する楽しみがある。こんな趣味を持つことに常にためらいを感じているが、もう少しやってみようと思う。もうすでに時代のほうはさらに進んでいて、ギターの売り上げが世界的に落ちて始めているらしい。そうなったら次は多分コンピューターを使った音楽の時代になるのだろう。人工知能が音楽を作ってくれる時代になるのかもしれない。究極のインチキ。魅力は感じないが、そういう時代だというなら仕方ない。人間らしく活動し、人間らしく存在するということについて、人間が敗北したのだ。
●お気に入り
わざわざこんな辺境なサイトを見てくれた目利きのあなたに、秀逸な音楽を紹介する。勿体無いことだが、世界のほとんどのことを我々は知らない。価値あるものをどこで見つけ出すことができるかを我々は知らない。世界全体に比べて一人の人間で知り得ることは針の穴よりも小さい。しかし探究心を捨ててはいけない。きっと俺の才能(あふれる才能が止まらねえや)も誰かが発見してくれるだろう。
① Alcest - Kodama

フランスのインディーズバンド。ネージュという才能のある人が中心となって活動している、ソロプロジェクトに近いものらしい。シューゲイザーとブラックメタルの合いの子、というような紹介を見かけるが、どっちも聴いたことがないから、そのへんのことはわからない。ちょっと聞きなれないうちはドン引きするかもしれない激しいデスボイスと、ささやくような歌唱法を場面ごとに使い分け、バンド演奏も激しさと静けさを同居させ、幻想的で独特な音楽世界を構築していく。すごい。
② Юлианна Караулова - Чувство Ю

ロシアのポップソング。ユリアンナ・カラウロワ、と読めば通じるんだと思う。なぜか最近ロシアの映画や音楽に興味があってネットで探しているが、この女性歌手は大変魅力的だった。この他にもНатали(ナタリー)とかЕвгения Отрадная(イフゲーニヤ・アトラドナヤ)といった歌手がいて、検索すればどこかで聴ける。アメリカや日本のポップスと大きな違いがないように見えつつ、どこか違う。ロシア語というだけでも新鮮で楽しい。海のすぐ向こうに広がる未知の異文化に思いを馳せようや。
③ Terry Bozzio - Chamber Works
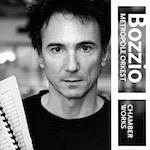
Terry Bozzioはタムやシンバルを無数に並べて巨大なドラムセットを構築する天才ドラマーである。バスドラムやタムをMIDIにつないで音階演奏をできるようにし、ドラム一人とは思えないようなメロディックな演奏を繰り出してくる。オランダのオーケストラと共演した本作は芸術性が高くて一般受けはしないだろうが、気にいる人は病みつきになるかもしれない。ロックの感覚をしっかり留めつつ、民族音楽や20世紀のクラシック音楽などの雰囲気を含ませている。21世紀初頭を代表する音楽として是非記憶に刻まれてほしい。
④ Kamen & Hotei - Guitar Concerto

ハリウッド映画の音楽を手がけてきた作曲家Michael Kamenはクラシック系の人だが、ロックにも詳しく、メタリカとオーケストラの共演なども実現させている。メタリカとの共演が全編に渡ってかなり激しいのに対し、このGuitar Concertoは緩急のある上質な音楽として丁寧に仕上げられている。繊細に始まり壮烈に終わる抑揚の効いたギターソロ演奏にハンカチ必須。バンドとオーケストラがぶつかり合いながら調和し、唯一の音楽になっている。古典的な3楽章構成。20世紀末の音楽として、忘れ去られることなく残ってほしい。
⑤ melanesian choirs - the blessed islands

シンレッドラインという映画で使われた音楽。太平洋戦争の戦場になったメラネシア諸島の先住民族によるアカペラ合唱。現地の伝統音楽というより、明らかにキリスト教が伝播してできた教会音楽のおもむきになっている。いつ誰がこのような音楽を教えたのか。老荘思想を体現したような自然の生活の中に、なぜこれほど高度な(人工的な)西洋音楽が根付いたのかを調べると、深い歴史があるのかもしれない。
⑥ Dmitry Andrianov / Feodor Dosmov / Sergey Golovin

ロシア人ギタリストを3人ほど。どなたもiTunesなどで聴ける。Dmitry Andrianovは歌うようなギターメロディ、曲の盛り上がりにつれて技巧を見せるソロの加減が心地いい、最も好きなタイプのギタリスト。Feodor Dosmovは「Impact Fuze」というトリオバンド名義でアルバムを出している。頭から尻尾まで変拍子・難しげなコード理論なんでもありの超絶技巧フュージョン。Sergey Golovinはメタルの中でも特に激しいメタルギタリスト。8弦ギターを使って変拍子の上を縦横無尽の演奏する、マティアス・エクルンドを思い出すタイプ。上に紹介したロシアポップスと違って、名義とタイトルは英語で検索しやすい。インストに国境はないのだ。
※追記:あの近くてよくわからない面白そうな国が戦争に至ったのは悲しいことだ(2022/3)
●たらこスパゲティの作り方
・材料・・・スパゲティ、たらこ、バター、塩、あらびきコショー、チューブにんにく、顆粒だし、刻み海苔
①お湯を多めに沸騰させて麺を茹でる。太い麺がいいぞ。
②茹でるのを待っている間、たらこを皮からほぐし、ボウルの中にたらこと調味料と少量の茹で汁を投入する。量は直感でいい。それでできた味が、あんたの味なのさ。気分次第でマヨネーズや砂糖を少しずつ入れてもいい。
③茹でたスパゲティをボウルに投入してよく混ぜる。たらこが白く加熱されるので、たらこの生っぽさを大事にしたいときは、少しだけ麺が冷めるのを待ってからたらこを和える。明太子でもいい。
④食器に盛り付ける。刻み海苔を忘れてはいけない。好みよってはレモン汁を少し。予算を削って1/3バターやマーガリンを使うと、すんげえマズい。ときどき食べる嗜好品だと思って、スパゲティには本物のバターを使わなければいけない。
●ドラゴンクエストを熱く語る

■序
ドラゴンクエストというゲームを、プレイしたことがない人はいても、そのタイトルを知らない人は少ないと思う。この人気シリーズの第一作目はファミコン時代に登場した。容量がわずか64KBしかない非常に厳しい条件の中で、まだ認知されていないRPGというゲームジャンルを広く浸透させた、ゲーム史に燦然と輝く名作である。
内容は非常にシンプルで、ある日「竜王」という名前の大魔王が突然復活して世界が闇に閉ざされる。大魔王の根城はマップ中央の島にある。プレイヤーは王様の命令で勇者の子孫と呼ばれる少年を東西南北に旅をさせる。各地で遭遇するモンスターを倒し、倒すごとに、力とか素早さといった能力値が少しずつ上がって強くなる。そして各地に散らばる「秘密のアイテム」を集めて大魔王の島に橋をかけ、これを討伐せしめ世界を平和にする。それだけのゲームなのだ。
■王様の教育論
王様は勇者の子孫という、まだヒヨコのような少年にわずかな資金を与えて広い世界におっぽり出す。その資金で「ぬののふく」と「こんぼう」を装備して何度も死にかけながら旅をする。どうしてこんなにひどい放任なんだろう。人類の未来がかかっているのに、どうして勇者の子孫という期待の星に潤沢な装備品と護衛の兵をつけないのか。しかし今よく考えてみると、事情は案外深いのだ。王様は優れた教育者だと思う。まるでひどい放任のようだが、ちゃんと目をつけていて、本当に危なくなったら(死んでしまったら)助けてくれる。所持金の半分を没収して、愛情あふれるシュールな叱責を飛ばしてくれる。この「死んでしまうとはなにごとだ!」という叱責はドラクエファンの間で長く語られている。そこに愛があるから人々の印象に残ったのだ。おかげで少年はちゃくちゃくとタフになって「少年」から「勇者」になり、竜王を退治して目的を果たす。そして今度は自分の土地を探したいという第二の旅の門出を祝福してラッパ隊と一緒に見送ってくれる。こんな器の大きい大人は現実に滅多に出会えないだろう。普通の大人だったら「お前には無理」「そんな危ないことしてはいけません」「そんなに行きたけりゃ自己責任で」というところを、王様はいきなりおっぽり出して最後には見事な結果を出した。少年の現時点の能力と未来の可能性を見抜き、過干渉せずに信頼する。よほど偉大な人物だったに違いない。

■戦略と思想
大魔王はどうして組織的に部下のモンスターを指揮して人類を滅ぼさないのか。どうして王様は組織的に抵抗の指揮をせず、座して滅びるのを待っているのか。それは誤解というものだ。両陣営の戦略を読み解いてみたい。竜王の根城はマップ中央の島にある。強大な力をもっているとは言え、東西南北を敵に囲まれた状態でいきなり復活した状態では、さすがにうかつな行動はできないはずだ。そこで、すぐ対岸にある人類の首都(地点A)を襲撃すると見せかけて人類を戦々恐々させ、しかしスライムなどの弱いモンスターしか配備させない。攻める気があるのかないのか、困惑させたところで城を急襲してヒロインのローラ姫をさらって東方の洞窟(地点B)に閉じ込めてしまう。こうして人類の注意を中央の首都と東方に向けたところで、南西にある砂漠の街(地点C)を襲撃して滅ぼしている。見事な陽動と雷撃戦ではないか。マップを見ると、南北を往来する旅人にとってこの砂漠の街は重要な拠点だっただろう。こうして人類の支配域を南北に分断させ、逐次占領域を拡大していく。これは沖縄戦や満州侵攻でも採られた作戦で、紀元前の春秋戦国末期には秦が韓を南北に分断してから滅亡させた歴史がある。
人類側はどう考えていたか。まず兵員と物資を首都に集中させていない。東京のように一極集中させれば、そこだけは発展するが、巨大地震やミサイルがやってきたら日本全体がオダブツになってしまうだろう。まずはそのようなリスクを分散させている。南方のメルキドという城塞都市(地点D)は特に強力な軍事要塞になっていて、うまくいけば竜王の島を南北から挟撃できるかもしれない。竜王の島に渡るための「秘密のアイテム」も各地に分散させているのは、下手に橋をかけてしまえばそこから東方にモンスターが殺到してしまう危険があるからだ。こうやって直近の危機を回避するようにして、次の戦略を考える時間を稼ぐ。遠い南方にあるメルキドを特に強化しているのは、そこに強いモンスターを配備させる根回しなのだ。おかげで首都周辺は割と平和でいられる。
こうして東西冷戦のような大局的こう着状態にした上で、刺客の派遣を決定する。勇者のことでありますね。首都周辺で弱いスライムなどをやっつけて少しずつ強くなり、北方へ旅してまた強くなり・・・と繰り返して最後は敵の根城に潜入する。竜王だって指をくわえて退治られるのを座して待っていたわけではない。なんせ歳が若いのだから「世界の半分をわけてやる」などと誘惑すればダークサイドに堕ちて味方にできるだろう。それを拒否するなら巨大なドラゴンに化けて喰ってしまえばいい。ところが勇者は誘惑にも乗らず、ドラゴンに化けた竜王を退治してしまった。計算以上に少年は強くなっていたのだ。これは先に述べた王様の功績である。誘惑に乗らなかったのはローラ姫の愛のおかげである。
わずか64KBの世界にこれだけの戦略と人間ドラマが込められたこの不朽の名作を少し理解していただけただろうか。一作目にして全てが入っている。ゲームは虚構だが、すぐれた虚構は現実を見る手がかりになる。リメイク版が出ているぞ。さあ、電源を入れよう。勇者とは、あなたのことなのだ。
●うどんの作り方
・材料・・・小麦粉、塩、温水
①小麦粉に塩水を少しずつ加えてこねる。入れすぎると柔くなるので注意。
②手でもいいが、足でこねるときは衛生に気をつけてくれ。水虫菌は50度で死滅するらしいぞ。
③丸めた状態で1〜2時間ほど常温で寝かせる。
④打ち粉を多めにふって、薄く広げて細く切る。打ち粉が足りないとくっつくので注意。この工程が難しい。
⑤麺の太さに合わせて10分程度茹でる。
・めんつゆの材料・・・しょうゆ、みりん、酒、顆粒だし
①みりんと酒を鍋で沸騰させてアルコールを飛ばす。
②しょうゆと顆粒だしを投入。各材料の配分は各自で研究する。砂糖を入れると市販の味に近づく。
③ざるうどん、かけうどんなど食べ方に合わせて薄めて使う。
→結論・・・意外とうどん。
●缶詰理論
私は缶詰が好きだ。味が、というより、あの極度に長持ちする保存性に不思議な魅力を感じる。歳暮や中元のギフトをいただけるなら「箱入り缶詰セット」が嬉しい。中身の品質だけでなく、ラベルのデザインに渋みと深みがあるものが望ましい。札幌駅の道産品ショップで売っていた占冠村のエゾシカの缶詰や網走の鯨の缶詰は秀逸な逸品だった。こういうものを買って食べるというより眺めるのが好きなのだが、それは多分、この小さい缶の中に生命の維持に必須の食料がギッシリ詰まっているという「ボク宝(国宝より大切なボクの宝物)」感に陶酔しているのだと思う。中は真空・殺菌済みで腐敗しない。つまり缶の中は時間が停止している! この「タイムカプセル」感。空腹を満たす食材が、時間が停止した缶の中で眠っている。それは永久にあなたを待っている。敦煌遺跡の膨大な教典のような時空のロマンが、そこにある。
時間を停止させる、という実現不可能な願望を人間は常に抱いていると思う。時間の流れというのは老いや死を恐れる我々人間にとってやっかいなもので、古代からずっと人類は不老長寿の方法を必死になって探ってきたのだ。人は変わっていく。自分も変わるし、周りの環境も変わっていく。万物は流転する。これに例外はない。今まであったものが永久に変わらなければいいのに。昨日まで続いた平穏な日々が変わらなければいいのに。と願うのは人間として避けられない。はかなく変化していく頼りない世界に生きる人類は、「変わらないもの」に憧れを持つ。写真を撮って残すとか、古い文化遺産を当時の原型をなるべく残したまま保存するとか。急激な時代の変化に拒否反応を示すこともある。変化というのは確かに人間に不安をもたらす。それが取り返しのつかない破滅的な変化である可能性も常に抱えているのだから。
そんな中にあって缶詰というものは、食料という最も変化(腐敗)の早い物であるにも関わらず、なんと賞味期限が3年という長期間に設定されている。実際にはそれよりもはるかに長く保つと言われている。この缶詰が手元にある限り、今日世界が破滅して想像を絶する困難な日々が来ても、明日一日は空腹を回避することができるだろう。缶詰を買うというのは、単に食料を買っているのではなく、極限の破滅の時が来ても安心していられる一日という「時間」を買っているのだ。
災害に備えて缶詰を備蓄するときに、何か名状しがたいウキウキ感を感じるなら、あなたは缶詰の魅力を知っている。缶詰は、あなたが開けるのを待っている。と同時に、永久に開けるのを拒んでいる。缶詰はあなたの空腹を満たす使命を持ちながら永久に眠り、そしてあなたは開けない缶詰によって永久に満たされているのだ。
●希少な豆の話
都会に住む人はたまに田舎で畑仕事でも手伝ってみるといい。気づくことがいろいろある。豆の生産が面白かった。豆は油脂性のものと炭水化物性のものの2種類に大別される。大豆は前者で、あずきなどが後者にあたる。北海道北見市の名産品である白花豆や紫花豆も後者にあたるもので、茹でてつぶせば餡になり、あるいはマッシュポテトの代わりとして捏ね上げればコロッケになり、ドーナツなども作ることができる。生産は非常に手間がかかり過酷で、関係者は口を揃えて「割りに合わねえよ!」と叫びたくもなるのだが、そうやって生産されるこれらの豆は栄養価も高く、日持ちもするので常備食としても極めて優れている。「べにや長谷川商店・豆料理」という本には、かなりの種類の豆が紹介されている。
このような豆は在来種と呼ばれるもので、本来は外来のものだが、その土地に持ち込まれ、世代を経て環境に適応した新しい品種らしい。多くの農産物で各地に固有の在来種が存在する。全国的な知名度は低くても、その土地でしか生産されない極めて貴重な産物であり、その土地の食文化となっているのだ。このような自然の多様性と、それと共生してきた先人の工夫を忘れてしまうのはもったいない。その土地の文化というものは、外の世界との交流によって「原料」が持ち込まれ、その土地で固有の変化を起こすことで発展する。文化とは「昔からある固定したもの」とは限らない。文化とは交流から常に生まれ、常に変化していくものであり、その多様性を無視してはならないと思う。もちろん、それによって失われる文化もあるだろうということは難しい問題かもしれないが。
時々、大量の家畜が病気で殺処分されるという報道がある。生産性を重視し、単一の品種に揃えたことによる脆弱性だと言われている。多様性こそが世界の強さと豊かさの根本であり、それは文化においても変わらないと思う。多様な価値観、多様な人間を異端として排除するような強権的な社会は長くは続かない。一律にロボット的な思考と行動を強要され、抑圧され続けた人間の精神は、限界が来ると暴力的な態度も辞さなくなる。「遊ぶこと」が大切だ。そこで私は、どうせ社会に適応できないし、一人でニッチな作品制作にとりかかることにした。常に迷いがあり、自分のやっていることに価値があるのか確信はないけれど、当分はそれで胸を張る他ない。聴いてくれる人が全然いなくて割りに合わなくても、やめようとは思わない。大したものは作っていなくても、完成したときの喜びは大きい。
●揃えて縮めて読書して
李御寧(イー・オリョン)著「縮み志向の日本人」という文化論の本が大変に面白かった。日本人は外国から文化を輸入するが、それを必ず縮めようとする傾向があるという。ラジカセ(もう古いけど)などがわかりやすい例で、これはラジオとカセットプレーヤーとスピーカーを一体化させて、コンパクトに仕上げている。ウォークマンは、大きなオーディオプレーヤーを飛躍的に縮めてポケットに入るほど小さくしたスグレモノだった。もっと古い例では、中国大陸から「うちわ」を導入し、それを小さく折り畳むことができる扇子に発展させた。長安の都を模して平城京とか平安京とかいった都を建設するのも、土地が狭いからギッシリ縮めるしかない。遣隋使だとか遣唐使だとかを派遣していた日本の歴史を想像してみると、長い歳月と命をかけて文化・知識を輸入するわけだから、そうやって手に入れた成果は一滴も無駄にはできなかったはずだ。その性格が今も残っているのだろう。
日本人はおおむねの傾向として、得た知識を無駄なく活用し、一つに絞ることなく多様な要素を詰め込み、それを小さく洗練させてものを作ろうとする。べつにそれが立派だとか悪いとかいうのではない。そういう性格だというだけのことだ。マーティー・フリードマンというアメリカのメタルギタリストは日本のポップスが非常に好きで日本にやってきた人で、さかんに日本のポップスを褒めているが、その主旨は「一つのアルバムの中に多様な音楽要素が含まれている」ということだった。メタルバンドならメタルだけ、ブルースならブルースだけ、という一つのスタイルに収まらず、多様なアレンジを見せるのが日本のポップスの特徴だそうである。
音楽の勉強をしたとき「ギターをやるならブルースは必須」とか「ポピュラー音楽を知りたければジャズは必須」とか、もうとにかくいろんなものが必須だと言われ続けたことがある。こっちも素直で勤勉な性格だから律儀に学んだけれど、義務感でやるから、つまらなくてほとんどモノにならなかった。それでも、自分の作品を作るときには、それまで習得した知識を少しでも多く詰め込もうという傾向が現れる。小さな媒体の中に多様な要素をギッシリ詰めることに美学を感じるという点で、どうも私は典型的な日本人なのだと思う。
日頃、小さい物を偏愛している。愛用品は直径15センチ程度のスキレット(鉄のフライパン)と土鍋(ゆず天目)で、あまりにも小さいので食材を切りすぎるとすぐに溢れる。すぐに腹が減る。しかしこの愛用はやめないと思う。最小限の道具で工夫して多彩な成果を出そうとする生活は楽しい。最近、ようやく小さい本棚を買うことができた。引越し時に一人で運べるぐらいの小さいものにして、古典から現代のものまで好奇心に任せて色々詰め込んである。その本の並びを見るたびに、小さな枠の中に詰め込まれた奥深さとその喜びを感じるのだ。
●アナログ回帰
子供の頃はちょっとしたパソコン少年だった。NECのPC98というのがあって、電源を入れると真っ暗な背景にプログラミングの画面が出てくる。これは一体何か?と訊くと、ここにプログラムを打ち込んでいけば、その処理を行った結果が画面に表示され、高度にやれば簡単なゲームだって作れるという。プログラミングの教本があって、その通りに打ち込んで行けば、理解はできなくてもそのプログラム例のゲームを作成することができる。私は感動した。ファミコンで遊ぶのも面白かったが、ぜひ自分で作りたいと思った。学校の友人との付き合いは適当に済ませて、この遊びに熱中した。
ワープロもよく遊んだ。自分の書いた稚拙な駄文が、綺麗な活字になって印刷される! 小説の執筆と歴史書の編纂に挑戦したが、さすがに無理だった。シャープのザウルスという端末もあった。これはスマホの形をしていてニンテンドーDSのようなタッチペンで操作する「電子手帳」だった。物珍しくて弄り倒した。そのうち電気屋の広告でザウルスの新機種を知った。なんとカラー画面でデジタルカメラまで搭載されているらしい。なんてすごいんだ。こいつに電話機能とか、銀行口座に通信して支払いする機能とかとにかくなんでもつければ楽しいじゃないかと思った。スマホのようなものを想像して勝手に感動していた。
そのうちWindows95が流行っていよいよハイテクな時代だと思った。と同時に、あまりにも早く変化していくこの世界に次第に興味を失っていった。パソコンのスペックはどんどん上がって行くし、OSも新しいのが出てくる。通信速度も上がっていくし、その通信の用途も広がっていき、ネット通販も当たり前になった。とうとう動画を見るのに不自由しない通信速度になった。もうパソコンの進化は少なくとも私ら一般人には必要ないだろう、と思ったところでスマートフォンが登場してそれが当たり前になった。いずれこれも廃れてもっと小さい便利なガジェットが普及するのだろう。「もういらねえよ」という気分になるのが健康的ではないかと思う。私はスマホを持っていない。恐ろしく些細なことまでコンピューターで管理されている社会に生きていると、半分死んだような気分になってくる。産業革命や原発事故が教えてくれたように、テクノロジーの発展には恩恵と弊害が必ず発生する。これからどういう時代が来るのか、あまりいい予感はしない。
最近、アナログ回帰という言葉を目にした。なんと昔レコードプレーヤーを作っていた会社が何十年ぶりで生産を再開したという。それも、時代についていけない年配世代の懐古趣味ではなく、若い世代が面白がっているのだと。さらに面白いと思ったのは、ネットを通じて「あなたのオリジナル曲をアナログレコードにして送ります」という業者を見つけたことだった。自分で作成したPDFファイルを印刷・製本してくれる業者も増えた。デジタル技術を駆使しつつ、アナログを楽しむ時代になってきているのだ。単に時代についていけない後ろ向きのアナログ回帰ではない。先端のガジェットを一応知りつつ、同時に本当に人間に必要なのは何か、ということを考える時なのかもしれない。人間の身体はデジタル機器ではない。君は心を持った人間なのだというチャップリンの演説が胸を打つ。Youtubeで見られるぞ。